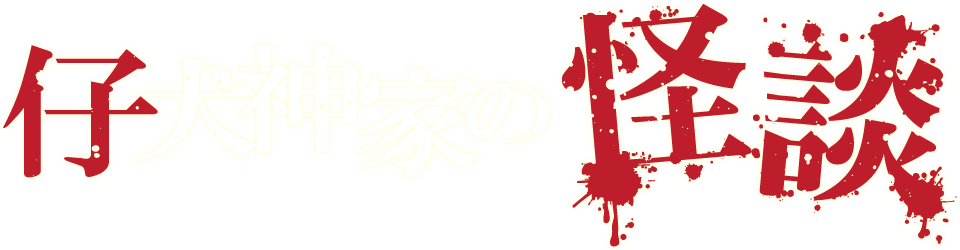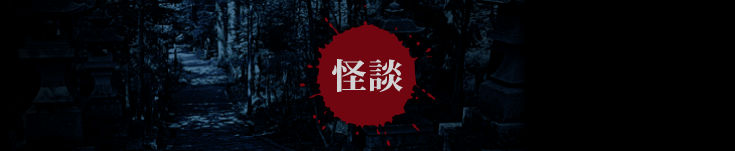以前勤めていた会社を退職して以降、再就職もせずにフラフラとフリーターをしていた物流倉庫。ある日の休憩時間、喫煙所で先輩の上田さんに声を掛けられた――。
「君さ、霊感とかあるの?」
この頃私は職場の仲間達に、学生時代には心霊スポットなる場所に、それはもう足繁く通っていたという話を披露していた。それをたまたま傍で聞いていたのだろう。
私自身、心霊といった類に興味はあれど、実際にナニかを見るだとか、ナニかを聞くだとか、そういった体験は皆無に近かった。これは正直残念であるが、興味がある者に限って、そういうモノだ。
なので、霊感といった物は持ち合わせてはいない。それを伝えると――。
「そっか……、最近ちょっと気になる事があってな」
「良かったら聞いてくれないか?」
こちらの返答も待たず、上田さんは静かに語りだした――。
上田さんの出身は岩手県。彼の実家は先の東日本大震災の被害に遭って、津波で流されてしまった。
その際に父親が行方不明となっており、どこかでまた会えると僅かな希望を抱きつつ、数か月が過ぎていた。
そんなある日、地元に残っている兄から1本の電話が入った――。
「親父が見つかった……。葬式をしようと思うんだが」
どこかで覚悟はしていたし、心の準備も整ってはいた。
上田さんは、自分たち兄弟をしっかりと食わせてくれた父親の事を人並みに尊敬をしていたし、若い頃は数えきれない程の衝突もあったが、それなりに好きだった。
肉親の死である。それ相応の物悲しさを感じながら、すぐにでも実家に戻ると兄に伝えた。
翌日、上田さんは会社に事情を話して1週間の休暇を取り、妻と2人の子供を連れて岩手に帰省する事になった――。
復興への動きが本格的に始まった頃の岩手県。
久方ぶりに帰ってきた故郷で兄と再会し、積もる話も止まらなければ、子供達も久々の田舎だという事で従弟たちとの大はしゃぎ。
すでに葬式の段取りは整っているという事で、ザッと実家に荷物を置いて、一家は喪服に着替えてすぐに地元のセレモニーホールへと向かった。
数年ぶりの父親との対面。
遺体の状態が、あまりにも原形を留めていなかった事もあり、血縁者の大人のみが確認をした。しかし、正直それが本当に実の父であったのか、目視での確信は持てなかったという。
親戚や地元の友人が多数集まった葬儀は思いのほか賑やかなモノになり、夕方過ぎには呑めや騒げの大宴会が始まった。
再会した親戚や、幼少の頃から世話になった近所の爺さん婆さん、酒で顔を真っ赤に染めて、思い出話に花を咲かせる大盛り上がり。
数時間が立つ頃にはポツリポツリと帰宅をしたり、その場で眠りこける者も出始めてきた。
夜も更けてきた頃、上田さんは兄にそっと肩を叩かれた――。
「東京からの長旅ご苦労さん、もう疲れただろう?お前はゆっくり休め」
「寝ずの番は俺がやるからよ」
上田さんも大の酒好きだった。兄の申し出に甘えさせてもらう形で、いい気分のまま横になり、眠った――。
どれほど眠っていただろうか。
深夜の2時か3時か、誰かに体を揺すられる感触があって、上田さんは目を覚ました。
兄が起こしにやってきたのだ。
何用かと尋ねてみると、ちょっと親父の所に来て欲しい、そう頼まれた。
腫れぼったい瞼を擦りつつ、兄の後を付いてフラフラと父親のいる部屋へと向かい、棺の横のパイプ椅子に腰を掛ける。
兄が缶ビールを差し出してきた。
上田さん自身もそうだが、喪主を務めた長男である兄にも、積もる何かがあったのだろう。寝起きだし酒はもうお腹いっぱいだと思いつつも、久々の晩酌に付き合う事にした。
感傷に浸る様な顔つきで父親の話を始めた兄に、うんうんと相槌を返す上田さん。
眠気も酒の残りもあり、話半分も聞いていなかったが、ある瞬間に――。
「お前には聞こえないのか?」
眉を顰めた兄に問われた。
ハッとした上田さん。ごめんごめん、ちゃんと話は聞いてるよ、そう返すと――。
「お前、本当に聞こえてないのか?」
再度確認されるように問われる。強めな口調だ。
さっきから何言ってるんだよ兄貴?と、逆に問い返してみると――。
「シッ!!」
兄は人差し指を鼻の前に立て、声を出すなという様な仕草を取った。
部屋が一瞬「シン……」と無音になったその時――。
「ヒタッ……ヒタッ……ヒタッ……ヒタッ……」
何か、足音の様な不気味な音が耳に入ってきた。
「ヒタッ……ヒタッ……ヒタッ……ヒタッ……」
ツヤツヤな石タイルの床を、汗ばんだ素足を張り付かせて歩くような、そんな足音。
上田さんと兄の目が合う。おそらく兄は1人で寝ずの番をしている段階で、この音に気が付いたのだろう、息を呑むような表情をして小声で問いかけてくる――。
「いるよな……」
「ヒタッ……ヒタッ……ヒタッ……ヒタッ……ヒタッ……ヒタッ……ヒタッ……ヒタッ……」
部屋の中をグルグルと歩き回るように音が回る。
自分たち兄弟と父親の亡骸は、その円の中に収まる状態で音に囲まれている。
上田さんは飲みかけのビールを「グイッ」と飲み干して立ち上がり、気味が悪いから部屋に戻る。そう言うと、兄は――。
「俺は朝まで、此処に居るよ……」
なんだか遠い目でどこかを見つめながら、パイプ椅子に深く腰を掛け直した――。
最近こんな事があったんだと、上田さんが話してくれた――。
「あの足音」
「親父が会いに来てくれたんだと思えば、それは美談みたいになるけどな」
「どうも雰囲気というか、感じるモノが、親父のソレとは違ったんだよな……」
「君はどう思う?」
私の答えに何か期待していたのか、少し浮かない顔で聞かれた。
セレモニーホール。多くの人間の葬儀が行われるこの場所には、様々な死因、いくつもの事情、そして数えきれない遺体がやって来るのだろう。
もしかすれば、時に死後の世界へと旅立つ前に会いに来るのかもしれないし、また別の理由で生者に近づいてくるナニかであったのかも知れない。